***
その家は 代々郡知事を務める一族が住まっていた。
政治力があったとみえ、 近隣の郡を合併しながら国のなかでも大きな位置を占めるようになった。
郡知事といえばたいそうだが、やっていることは むかしながらの徴税役人だ。
世襲も長く続けば いつか 民衆のためではなく、自分たちの安定と懐を肥やすことに力を尽くすものも出てくる。
「お決まりのパターンだ・・」
ニィはそう 思った。
隣の郡とこちらで 兄弟で仕切っているが その境界でもめている。
ただ つまらない兄弟げんかならほおっておけばよいが
ここにも裏で諍いを大きくする強欲の魔が存在しそうだ。
それを突き止めることが 自分の仕事なのだと 納得した。
ニィは 屋敷の離れをあてがわれた。
「しばらくの 仮宿だ・・・」
固く、冷たい寝台に倒れこみ 天井の梁を眺めているうちその日の疲れがドッと押し寄せてきたように感じた。
背中に疲れが溜り、引きずり込まれていく感覚・・・
***
「ニィはどこを向いているの? わたしは ニィのココロがほしかった・・」
ああ、エマ・・・どうして・・今のままじゃだめなのか・・
「君のココロが 欲しい」
ん・・誰・・?
自分のほほにかかってくる 金色の長い髪
耳元でささやく 低く 甘い声
「か・・み・・・」
***
浅い眠りの中の夢だった。
上半身をはね起こし ニィは両手で顔を覆う。
指のすきまから 盛大な自分自身を見る。
「ああ、俺ってばケダモノ・・・」
さっき 脳天がふっとぶかというほど
娼婦を相手に抜いてきたところだというのに。
娼婦は去ろうとするニィに這いずるようにすがって
タダにしてやるからもう一度とせがんだ。
目がおよいで ろれつもまわらないのに
「ソコ」だけは 淫魔のように 際限なく求めているようだった。
自堕落に生きる自分にはお似合いの場所だと
娼館にきたのに
娼婦のなりは 閉めたドア越しに聞こえたエマのすすり泣きを
思い出させるばかりだった。。
「ココロ、ココロって・・ どいつもこいつも・・・
俺のココロは ・・・どこに おいてきたのか・・」
両手で自分を刺激する。
エマを想った。
いつもの意志の強い目が 艶めいて潤む。
首筋の汗にはりつく髪。なめらかな肌。
足の付け根に口づけると悲鳴のような 細い声をあげ、
甘酸っぱいにおいの露は伝って落ちるほどあふれる。
「エマ・・エマ・・・」
ニィは くらくらするような快感を覚えながら
それが高まってくるにつれ 苦痛を感じて 歯をかみしめる。
「足らない・・・足らない・・・神!」
薄く目を開くと そろそろと 片手を おろしていき
双丘に指をしのばせていく。
いつのまにか エマは消え 胸をなぞる大きな手を想う。
口の中を蹂躙するやわらかい舌は 暴力的で しかし やさしかった。
圧倒的な強さで制圧するのではなく 包み込んできた。
そこに自分を任せる 浮遊感
ニィは欲情を吐き出したが
自分の奥底に焼き付けられた烙印が炎のように上がるのを感じていた
全身を虫が這っているようだ。
「欲しい・・・」
打ち消しても打ち消しても よみがえる。
「神・・」

寝台の上にまるまっていると
思わず涙がでて 自分自身とまどった。
「かわいそうにねぇ」
寝台の端に肘をつき 自分を覗き込んでいる目をみた。
ニィは全身の毛が逆立つような思いで 飛び起きた。
***
センチメンタルな気分は一瞬で消し飛んだ
。
ニィは寝台の上にあぐらをかき来訪者と向き合っている。
彼の背後には カーテンのない窓。
その夜の半月が投げ込む淡い光で 彼は闇の塊のように見えた。
彼が寝台の傍らの小さな椅子に座りなおす折
浮かんだシルエットの輪郭。
フードからさらりとシルバーの長髪。
斜めにこちらを向く目は一瞬の光を得てブルーだと確かめた。
ただし、そのブルーは黒の仮面の奥にあった。
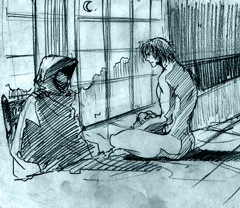
「たしかに ひんやりとはするが、 夏だぜ。
そのラシャのマントと仮面は 暑くねぇか?」
「暑いだとか寒いだとか、 さほど影響しないのは
お互い様だ」
「やはり同族ね。
なぜ きさまは そうして自分を隠す。
ペペを使って俺につなぎをとっていたのも きさまだな。
俺になにか 用があるなら言えよ。
こそこそかぎまわるな」
「悪いな。おまえの一部始終をみるのは おれの愉しみだ」
「ほぉ〜、てめえ、俺に惚れてんのか」
「そんなんじゃねぇ!」
ニィはかるい皮肉を言ったつもりだがまともにくってかかられたものだから
多少面食らった。
「あ・・あっそう、そりゃ残念。
きさま・・格好は仰々しいが、なんだ 俺と同じくらいか。
声はなんか・・こう、しわがれた感じだが」
「声?俺は声をもたない。しわがれた声というのは おまえの勝手なイメージだ」
「なにいってんだ、こうして 話しているじゃないか」
「俺の声は 奪われた・・」
「奪われた?」
「ともかく、俺はおまえの頭の中に直接話しかけている。人間には聞こえない。
人間と接するときには 文字でやりとりをする。
ペペが俺と話すのはあの子に流れる魔族の血のせいだ」
「おまえは 俺を知ってる。けど 俺はお前を知らない・・・。
名前は?これから先どう呼ぶ?」
「・・・・ニコ」
「ニコ・・・俺になんの目的で近づいた」
「おまえ・・ヴァルハラに帰りたいか」
「ヴァルハ・・って、俺が質問してるんだ!」
「なぜ 帰らない?」
「ちぇっ・・無視かよ・・
俺はヴァルハラには、帰れない・・」
「でも 帰りたいのだろう? いまだって・・」
「うるせえ!うるせえ! ああ、そうだな、かっこわるとこ みられちまっただろうし?
・・帰れないんだ。帰っちゃいけない。
帰ったとしても、 以前のようにクールにパートナーとして振る舞えるのか
自信がない・・」
「おまえのくちからそんな弱音を聞くとはな・・」
「ふん、知ったようなことを言うな。
おまえに 俺のなにがわかる・・・」
「わかるさ」
「おまえが 仮に 俺が神魔界を去ってからずっと付きまとっていたとして
その3年ですべてわかったなんて言われちゃ 俺がたまんねえよ」
「エマのことは 愛してなかったのか」
「いや、愛してたよ。ほんとだ。
はじめて そばにいたいと思った女だ」
「話せよ。話すことで 確認できる自分もあるかもしれない」